祖父母と別居してから1年ほど経ったころ、私たち家族は再び生活環境を変えることとなります。
祖母の説得により、父と祖父は和解し、私たちは祖父母の家の近くに家を建てて住むことになったのです。
私は元の保育園に戻ることとなり、また祖父母とも会えるようになりました。
幼いながら、慣れ親しんだ環境へ戻れたことに安堵し、嬉しかったことは覚えています。
幼稚園に上がるまで、私は両親ではなく、ほとんど祖父母の家で生活することになります。
祖母と同じ布団で寝たり、お風呂に入ったり、体調を崩して看病してもらったり、絵本を読んでもらったり…
祖母との思い出は沢山ありますが、母との思い出は思い出すことができません。
私は生後間もない頃から母よりも祖母と過ごす時間が長く、恐らく母よりも祖母との結びつきが強くなっていました。
私にとっての安全基地は祖母だったのです。
祖母が数日家を空けることになった時、不安で寂しくて、祖母に抱きついて大泣きしたことがありました。
母の前でワガママを言うことはありませんでしたが、祖母の前では自分の感情や思いを出していました。
ただ、祖母は過保護な一面がありました。
私にべったり張り付いて勉強をさせたり、私がノートに書いていたものを黙って見たりしていて、それがとても嫌でした。
祖母は怒ったり、厳しく躾けることはしませんでしたが、私を自分の理想とする良い子にしようとしていたように思います。
私は祖母のことが鬱陶しいけれども好きで、離れたくないというアンビバレントな感情を持っていました。
また私は親や先生など、大人の前では『良い子』でした。良い子を演じていたのだと思います。しかし、反対に友達の前ではワガママで、自分の思いのままに相手を動かそうとし、思い通りにならないと激昂する所がありました。
ここから分かるのが、私の幼少期は抵抗/両価型の愛着パターンを示す子どもに当てはまるということです。
「愛着障害 子ども時代を引きずる人々」(岡田尊司著)によると、「抵抗/両価型の親は母親自身不安が強く、神経質だったり、子供に対して厳格すぎたり、過干渉だったり、甘やかしたりする一方で、思い通りにならないと、突き放す態度をとるといった両価的な傾向が見られる。(省略)子どもは陰日向のはっきりした、二面性を抱えやすい」とあります。
幼い頃から良い子でいることを常に求められ、強制された結果、抵抗/両価型の二面性をもつ子どもになったと考えられます。
大人の前で抑圧された自分の感情や欲求を、友達にぶつけていたのです。
それでも私は祖母が大好きでした。私にとっては本当に大きな存在で、母親そのものでした。
なぜ私が祖父母の家で生活することになったのか、理由は覚えていません。
ただ、両親といるよりも祖父母といる方が居心地が良く、自然とそうなったのだと思います。
弟は私より幼く、母のそばにいるのはいつも弟でした。母は弟のものでした。
母は母なりに私のことを愛してくれていたと思うのですが、その実感が私にはありませんでした。
私は両親や弟は自分とは別の家族のように感じていました。
実際に両親、弟と共に食事をしたときに、私は父の機嫌を損ねてしまい、泣きながら祖父母の家に帰されたことがありました。
幼少期の私にとって両親の元に自分の居場所はなく、祖母の胸の中だけが唯一安心できる場所だったのです。
引用:「愛着障害 子ども時代を引きずる人々」 岡田尊司著 (光文社新書) P88-89








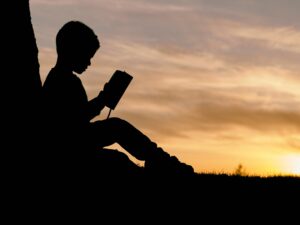

コメント