こんにちは。やなと申します。
私は看護師ですが、これまでいろんな病院で働いてきました。
働いてみると、それぞれの病院の良い所、悪い所が見えてきます。
これは一度就職して働いてみないと分からないことも多いです。
今回は私の経験からそれぞれの病院の特徴や内情についてお伝えできたらと思っています。
そして、これから就職される方や転職を考えておられる方の一助になれば幸いです✨
※ただし、ここに書くことは私一個人の独断と偏見であり、全ての病院に当てはまるものではありません。
また、私が経験した頃より年数が経過していて、変化していることもあります。
ご了承ください。
ここでは地方の公立病院と民間病院で比較していきたいと思います。
病院の規模としては、病床数200~350床くらいの規模を想定しています。
また、公立病院に大学病院は含んでいません。
なお、日本赤十字社が本社の赤十字病院もほとんど公立病院と同じ扱いと考えていただいて構いません。
新人教育
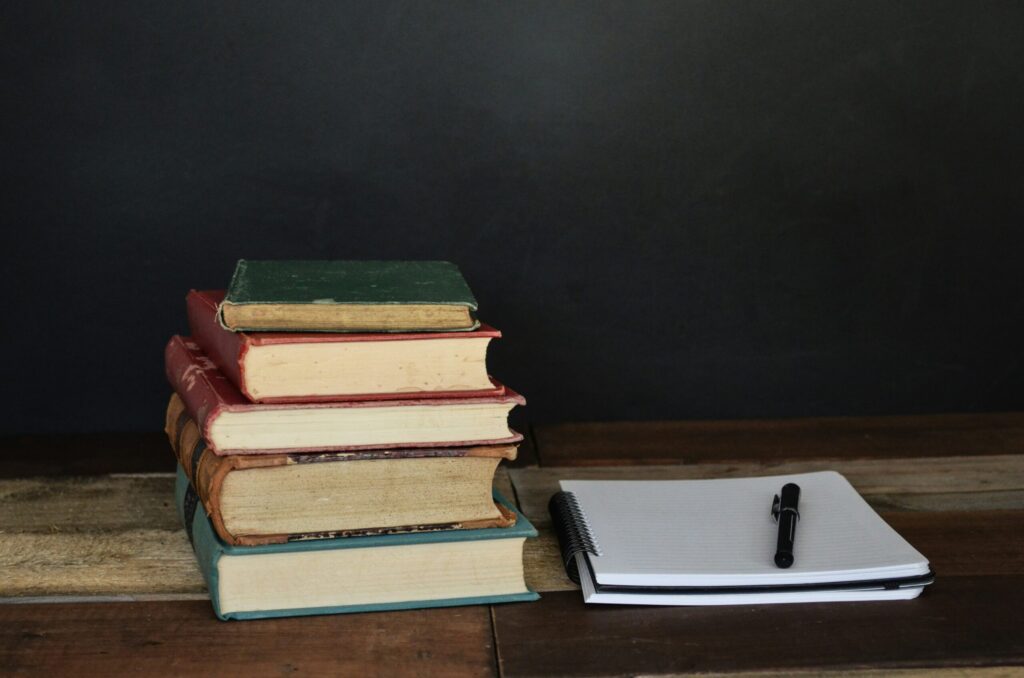
まずは新人教育についてです。
これは新社会人の方は気になるところではないでしょうか。
新人教育は看護師にとって本当に大事で、最初の3年間でどれだけ経験し、知識を吸収したかでその後の看護師人生に大きく影響してくると私は考えています。
というのも、看護師になってから3年目までは知識も技術も未熟なため、途中で退職してそこから新しい職場に転職することは少しハードルが上がります。
病院としては、中途採用者に即戦力を求めます。
基礎的な看護技術や知識は身につけていることを前提で採用するのです。
特に1年目で辞めてしまった場合、退職理由は次の転職にかなり影響します。
病院としても、出来るだけ辞めない人材が欲しいと考えているからです。
看護師不足ということもあり、新人以外に教育を行う余裕がないというのも理由の一つではないかと思います。
このような理由から、「看護師になった3年間は同じ病院で働いた方がいい」と言われています。
新人の方は特に、就職して最初の3年間は働き続けることが出来そうな職場を選ぶことは大切です。
公立病院
◎特徴
- 教育システムが確立されていることが多い
- 特に新人教育には力を入れていることが多く、集合研修やレポート提出が計画的に組み込まれている
- まずは研修を行ってから実践へと進むため、看護技術の習得ペースはゆっくり
- 技術チェックが厳しい
- 先輩が技術チェックをしてくれるので、不安は少ない
- 師長、副師長、リーダー、プリセプターと面談が頻回にあり、悩みや課題を共有できる
- 看護師ラダーに沿って教育を行ってくれる
ラダーとは:看護師個々の能力やキャリアを段階的に評価し、看護師の質の向上や成長を促すためのシステム
プリセプター制度:一人の先輩看護師がある一定の期間、一人の新人看護師に対して、マンツーマンで臨床実践を指導する方法
民間病院
◎特徴
- 病院全体での教育体制がないことが多く、新人教育の内容はプリセプターが決めていることが多い
- 新人看護師の人数が少ない場合は、新人だけの研修は行われず、看護協会や他病院の研修に参加することもある
- 看護技術の習得は実践を優先しており、技術の習得は公立病院よりも早い
給料

公立病院
公立病院で働く看護師は公務員の扱いとなります。そのため福利厚生が充実しています。
◎特徴
・公立病院の基本給の額はほぼ横並びで、どの病院も大差はない。
・給料に住宅手当や通勤手当も基本給に上乗せされる
・他の病院から転職したとしても、就労証明書があれば職務経験分の基本給を上乗せしてくれることがある
・互助会が冠婚葬祭の際に金銭的援助をしてくれる
→ 互助会で旅行に行ったり、スポーツクラブやレジャー施設の利用を割引してくれることもある互助会とは:加入者が一定の掛け金を払い込むことで社員のサポートをしてくれるもので、主に経済的な支援を目的としている
・専門学校卒、短大卒、大卒の順番で基本給が高くなる日本看護協会「2024年病院看護師実態調査」によると、新卒看護師の初任給は平均27万~28万円 (所得税や社会保険料が惹かれる前の金額) となっており、専門卒と大卒で看護師の初任給を比べると、大卒の方がやや高く、基本給で5917円の差があります。
・給料が毎年確実に昇給する公立病院に勤務する看護師の平均基本給与額は、新卒で約21~22万円、勤続10年非管理職で約27万円になっており、差は約6万円です。
民間病院
◎特徴
・専門学校卒も大学卒も基本給は変わらない。
・夜勤手当が公立病院よりも高い場合が多い。
・基本給の額は病院による。
・入社時に、自分の希望する給料を提示してもよい病院もある。
有給

夏季休暇
公立病院には一般的な有給の他に、夏季休暇というものがあります。
「夏休み」というやつです。
休暇の日数や取得期間は病院によりますが、日数はだいたい5日から10日間で、取得期間は6月から11月の間です。
まとまった休暇を取れるかは、病院や病棟によると思います。
事情を話せば、夏休みを利用して遠方の実家に帰省することも可能です。
子の看護休暇
日本赤十字社病院では、『子の看護休暇』が有給で受けることが出来ます。
子の看護休暇とは、小学校3年生までの子どもが病気やけがをした場合、看護を目的に取得できる休暇で、子ども1人につき5日間(対象となる子供が2人以上の場合は10日)取得できます。
ただし、この休暇を「有給」にするか「無休」にするかは企業の判断に委ねられており、65.1%が「無給」としています。
時短勤務
時短勤務とは、子育て中の看護師の勤務時間を短くしたり、夜勤を免除して働くことが出来る制度です。
正職員なのでボーナスは出ますが、短くなった勤務時間分の給料は欠勤として引かれるため、給料はその分少なくなります。
主にどの公立病院でも取得可能です。
物品

公立病院
治療に使用される注射器や針、点滴のルート、モニター等の医療機器のような物品は税金により補助されています。
もちろん、無駄遣いが許されるわけではありませんが、治療に必要なものは不自由なく用意されています。
3次救急の指定病院となれば、比較的新しい機器や物品が用意されていると思います。
吸引チューブ等は1回で使い捨てが多いです。
しかし、これも病院によって異なることもあります。
実際に私が勤務していた赤十字病院は、吸引チューブが基本は1日1本、繰り返し使用でした。
本当に病院の財政によります。
民間病院
民間病院は診療報酬に強く依存する構造のため、物品や機器の購入は公立病院に比べ慎重です。
「注射器1つ○○円」
と言う風に、病院全体で”コストカット”への意識は強いです。
実際に「使いまわせるものは、繰り返し使用する」という考え方です。
病院の規模が小さければ小さいほど、この考え方は強いと思います。
モニター心電図やシリンジポンプ、輸液ポンプも数が限られており、他の病棟へ借りに行くということもよくありました。
公立病院から民間病棟へ転職してまず驚くのが、物品使用への意識の違いかもしれません。
本当にカルチャーショックを受けると思います💦

コメント