私は子どもの頃、父の前では自分の気持ちや感情をおしころして生活していました。
父は自分の言ったことに家族が同意しない、あるいは不満があると感じるとひどく機嫌が悪くなりました。
父は一度機嫌が悪くなると謝っても許してくれず、何日も怒って口もきいてくれませんでした。
何に対して怒っているのか分からないこともよくありました。
暴力を振るわれることはありませんでしたが、怖い顔をして無視をされるというのは子どもにとっては恐怖でしかなく、私と弟は何とか父を怒らせないように気を遣っていました。
今で言うモラハラです。
母も父を怒らすと生活に支障が出ることが分かっていたため、父に逆らうことはありませんでした。
私たちに「お父さんを怒らせてはいけない」とよく言っていました。
父は健康のために週末になるとよく散歩に行きました。その散歩に私たちを連れて行くのですが、私はそれが本当に嫌でした。
というのも、その散歩は歩く距離が長く、10km近く歩く日もあったのです。
もう散歩ではありません。
私にだって休みの日にやりたいことはありましたが、この散歩に誘われてしまうと断るわけにはいきませんでした。
断れば、その日から何日も無視をされ、息の詰まるような毎日が待っています。
私たちは自分の気持ちをおしころし、行きたくもないのに嬉しそうに「うん、行く!!」と答えるしかありませんでした。
歩いている間も疲れた様子や帰りたい気持ちを父に悟られてはいけませんでした。
父は私たちが少しでも様子が違うと、自分に逆らっていると捉えるのです。
その他にも、次の日のテスト勉強をしていると父が買い物に誘ってきましたが、私は勉強がしたいからと買い物を断ってしまい、それが父の機嫌を損ねてしまいました。
しかし、テストで悪い点を取っても父の機嫌は悪くなるのです。
本当にめちゃくちゃです。
私にとって一番安全なはずの家が、まるで自分を試されているかのような、不安定で居心地の悪い場所でした。
父の前ではいつも気が抜けず、父を怒らせない答えを考え、間違えば罰が待っている。
子どもの頃から当たり前で気が付きませんでしたが、本当に異常だったと思います。
私たちは子どもは親に従うもの、自分の意思よりも親の意思が絶対で正しいと育てられました。
しかし、人間はどこかで自分の抑圧された感情や思いを発散するものです。そうしないと、爆発して自分が壊れてしまいます。
私は家の中よりも外で、つまり学校でストレスを発散していました。
これが、大人の前では良い子に振る舞い、友達の前では意地悪になるという歪んだ形で表出していました。
逆にどこにも発散する場所がなかったならば、私はもっと病的な症状を発症していたのでしょう。
子どもの頃の私には、外で発散するという方法しかありませんでしたが、友達には本当に申し訳なかったと今悔やんでいます。
「愛着障害 子ども時代を引きずる人々」(岡田尊司著)によると、「不安型の人は、相手の表情に対して敏感で、読み取る速度は速いものの、不正確であることが多い。ことに、怒りの表情と誤解してしまうことが多々ある。(省略)不安型の人は、自分が相手に送るメッセージに、相手が大きな関心を払っていると思いがちである。「相手によく思われたい」という自分の努力に対して、相手も同じくらい気を留めてくれていると期待するのである。」と記されています。
これはまさに私の幼少期そのものだと思います。
私は幼い頃から、父の怒りの感情に振り回されていました。
「父を怒らせていないか」「なぜ怒っているのか」「どうしたら、なんと謝れば許してもらえるのか」そんなことばかりを考えて生きていました。
どんな些細な表情や言動も怒りの表れのように感じ、恐れていたのです。
親は子どもの意思を尊重しなくてはいけません。
いくら子どもであっても、一人の人間であり、自分とは異なる個人です。
子どもには子どもなりの考えがあり、感情があり、意思があります。
もちろんまだ経験も知識も未熟であるため、親が正さなければいけないことはあるでしょう。
しかし、私は子どもが自分で考え決めたことは出来る限り尊重し、子どもがいつでも親にNOを言える関係でありたいと思います。
親子関係は主従関係ではなく、対等でなくてはならないのです。
引用:「愛着障害 子ども時代を引きずる人々」 岡田尊司著 (光文社新書) P226






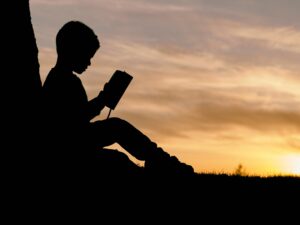


コメント